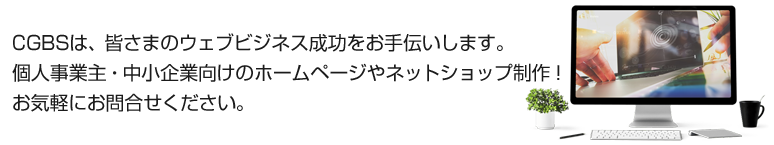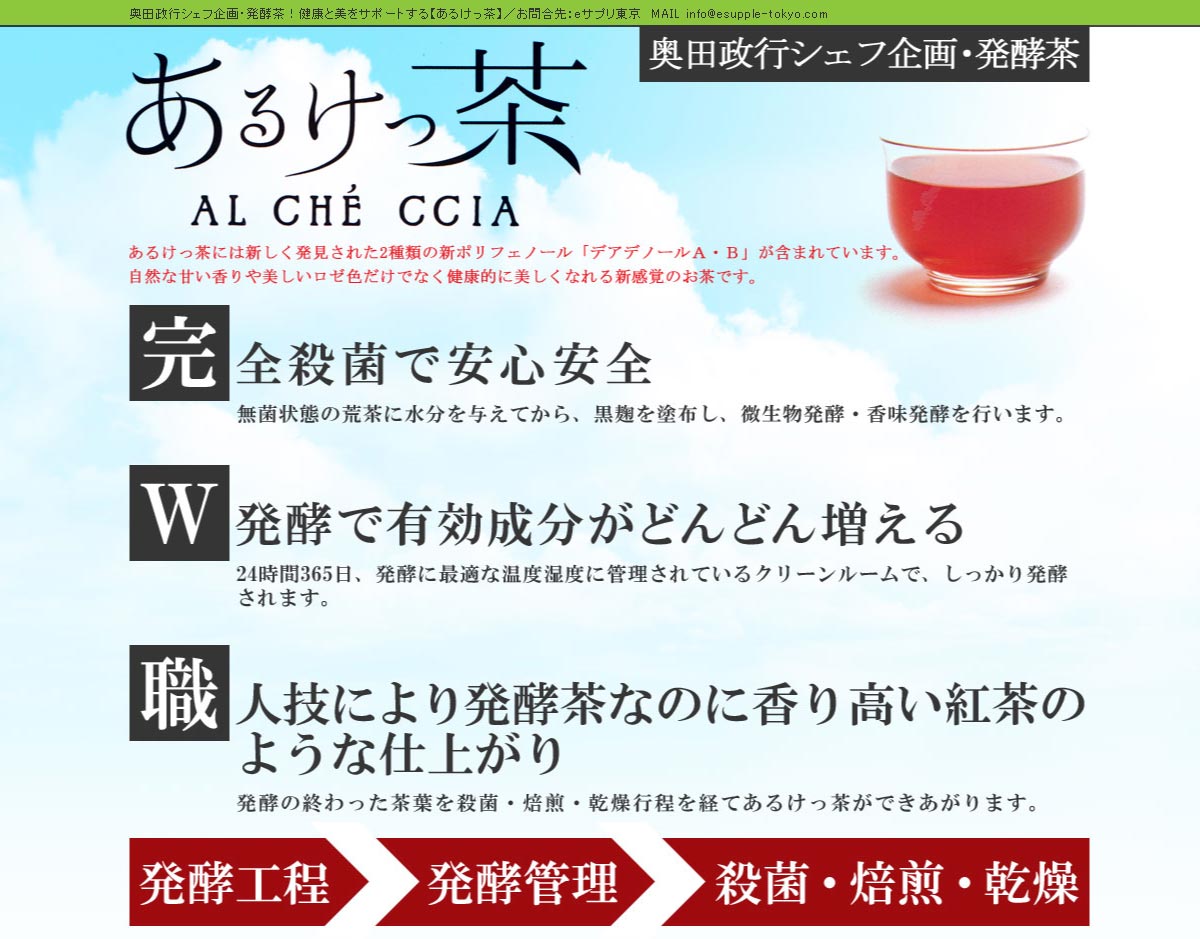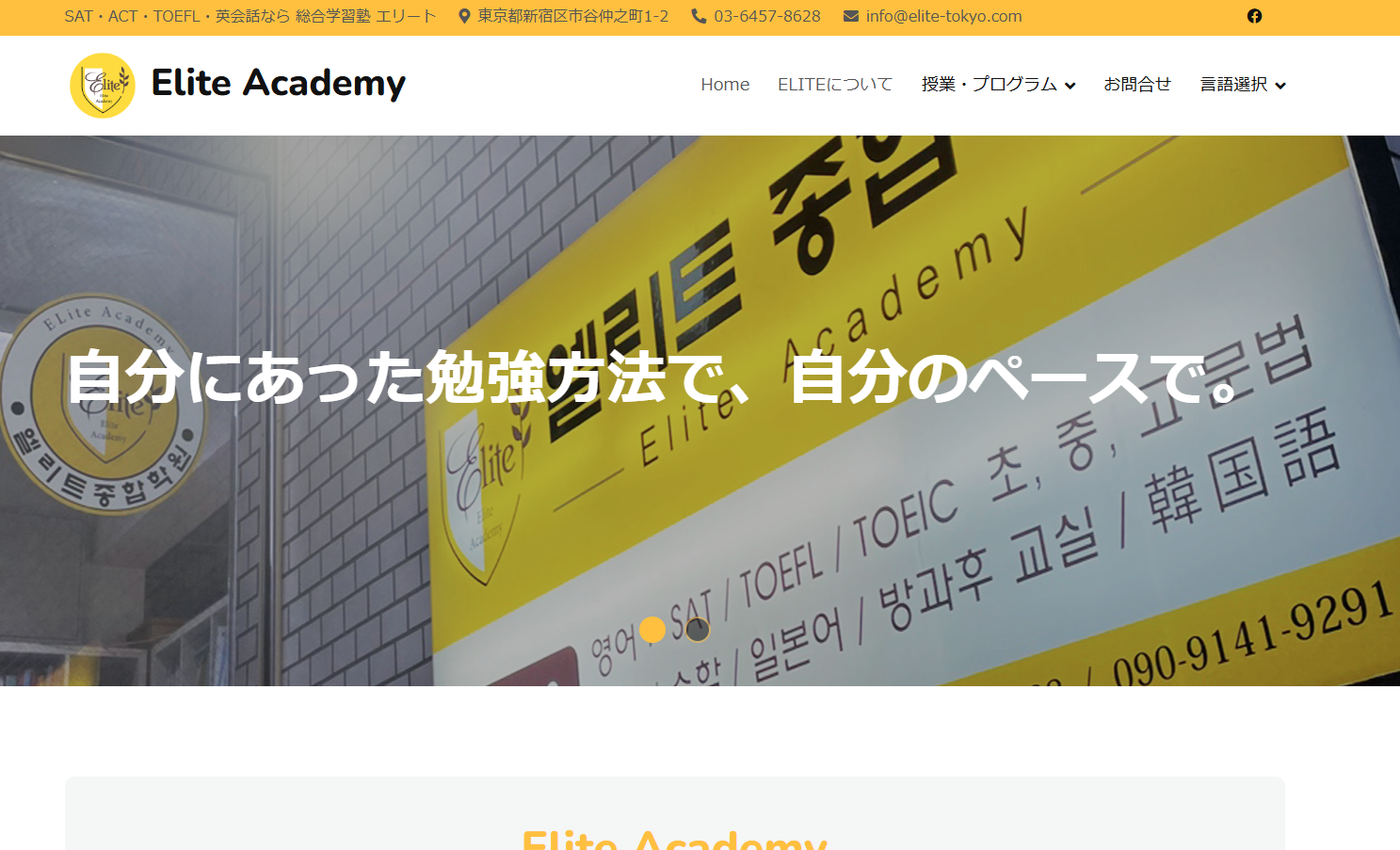江戸時代の商人たちは、事業を堅実で合理的に行っていたといわれています。特に古い商家には、経営の三大要素として「始末・才覚・算用」が伝わっています。この「始末・才覚・算用」は、これから独立・起業を目指す場合にも、成否を分けるポイントになるのではないでしょうか。
◇始末する −コスト管理−
始末とは、文字通り物事の始めと終わりです。始末するとは、商い(商売)において始めと終わりがピタリと合うように帳尻を合わせるという意味があります。また、江戸時代の商人たちは、始末を無駄を省き、質素と倹約を美徳として、物を有効に活用することと捉えていました。現代風にいえば、余剰のコストを抑えて利益を確保することといえます。
江戸時代の代表的な商人である近江商人の日常心得には、始末がありました。近江商人は元手の大きさが成功の鍵と考えており、その元手を減らすことはなんとしても避けようとしていたといいます。そして良品を薄利多売することを中心においた商法を実践していました。この近江商人の商法は、利が少なければコストを削減し経費を節約して、さらには生活を切詰めて始末をしていたのです。
ただし、近江商人の始末とは、単なる節約ではなく、消費する物の効用を使い尽くす、つまり物を本当に活かして使うといった意味もあったようです。
さらに近江商人は、倹約するだけではなく、有効と考えれば大金を使うことも厭わなかったことが記録されています。例えば、始末して財を成した近江の豪商、初代中井源左衛門は、寺社や公共施設に惜しみなく寄付し、四代目源左衛門光基も社会事業に巨額の私財を投じて社会に還元していたようです。
◇才覚をふるう−創意工夫−
才覚とは、商才ともいわれ、新しいビジネスやサービスを開発すること、また工夫と努力によってお客様を多く獲得して商売繁盛を図ることをいうようです。現代風にいえば経営革新といえます。
三越百貨店や三井財閥の元祖といわれる三井高利は、現銀掛け値なしの元祖ともいわれています。当時、人口増加が凄まじい江戸に目を付けて呉服店を出店したのですが、既存の大店と比べて資本力で劣り、呉服店の主な顧客となる大名家とその家中との取引の経験もありませんでした。
苦境に陥った三井高利は、既存の呉服商の商いの逆をいくことを思いつきました。つまり大名などの武家ではなく、一般町民に販売することを考えたのです。そして、特売価格で値段を付ける代わりに代金を現金で支払っていただく。一反単位でしか売らなかったやり方を改め、お客様が必要な分だけ売る。さらにその場で着物に仕立てることも始めました。これが三井高利が始めた現銀掛け値なしの商法です。
この商法は一般の町民に支持され、井原西鶴はその著書「日本永代蔵」で、江戸店では1日150両(現在では約750万円)の売上げがあったと書いています。そして三井高利を「大商人の手本」と評しています。
◇算用する−採算性−
算用とは、勘定や財政のことをいいます。勘定を精密に確実にして経理を誤らないことが大事であって、何事も算盤(そろばん)勘定するということを意味します。
簡単にいえば、算盤勘定に合うかどうか、採算性を確保するための商売の全体構想をいいます。現代風にいえば、経営計画・経営管理につながります。
短期的な利に敏いことの代表的存在である大阪商人ですが、実は長期的な算用でも優れた才覚を発揮していたようです。大阪商人は、「儲けるために働くのであって、損するためではない」との考えをもって商いをしていたといいます。1回の取引ごとに確実に利益を確保し、1件1件のお客様から僅かでも儲けさせていただく。これが商売を長く継続させるコツであると考えていました。
一方で大阪商人は、1回の取引ごとといった短期的な採算だけではなく、長期的な観点からの採算も重視していました。大阪の豪商・鴻池家の家訓には、「利益に目がくらみ、おぼつかない方との取引はしてはならない。間違いのないような取引のみにし、貸付金が大きくならないようにすること」(現代語訳)との教えがあります。これが一要因となり、鴻池家は倒産没落せず健全に続きました。
江戸時代の商人の経営の三大要素といわれる「始末・才覚・算用」について考えてまいりましたが、最近の経済事件を見ていますと、鴻池家の家訓にいう、「利益に目がくらみ、おぼつかない方との取引はしてはならない。」を忘れて、利益のみに走った不見識な経営者の多さが目立ちます。温故知新という言葉の通り、私たちも独立・起業を考えるとき、あるいは起業後の経営において、「始末・才覚・算用」という商いの三大要素を思い起こし、経営のあるべき姿を考えるべきではないでしょうか。
(後書き)本稿は当社顧問税理士の伊藤武彦先生からお届けいただいている「経営支援ニュースレター平成20年1月号」から引用させていただきました。